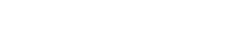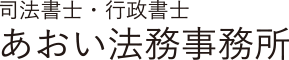最近話題のデジタル遺産について司法書士が解説します

デジタル遺産の時代です
スマートフォンやパソコンなどが普及した今ネット銀行やネット証券などを利用する方が増えており、「デジタル遺産」が注目されています。「どれがデジタル遺産に該当するの?そもそもデジタル遺産って何?」「デジタル遺産は具体的にどのように扱えばいいの?」など、分からないことも多く、どこから手を付ければいいのか困ってしまうことはないでしょうか。
デジタル遺産を何もせずに放置しておくと遺族にトラブルが起きることもあるため、今のうちに対策することが大切です。デジタル遺産について理解し、その種類、現状の問題点、生前に管理する理由や管理方法についてご紹介していきます。
デジタル遺産とはどんなもの?
デジタル遺産とは、故人の遺産の中で、パソコンやスマートフォンのデータの中で『直接金銭価値を持つデジタル形式で保存されている遺産』を指します。スマホの普及などにより「デジタル」で様々なものを管理する時代になってきています。
※デジタル遺品との違い
スマートフォンやパソコンで保存している写真や動画、ダウンロードした音楽データ、インターネット上に保存しているブログ、SNSサービスのアカウント、連絡先は直接金銭価値に繋がらないものをデジタル遺品と呼びます。
デジタル遺産の具体例
1.仮想通貨 ビットコイン(BTC)、イーサリアム(ETH)等
2.電子マネー(交通系電子マネーのチャージ残高Suica(スイカ)など)
3.スマホ決済 (PayPay、LINE Pay、楽天ペイ、メルペイ、d払いなど)
4.証券口座・FX口座(NISA、ネット証券等)
5.ネット銀行の口座(楽天銀行、ソニー銀行など)
見落としがちですが、故人の債務がある場合は、相続人が解約手続きをしなければなりません。そのままにしておくと月額料金が口座から払い続けられてしまうことがあります。
・定期サービス(携帯電話、公共料金、サブスクリプション契約(動画や音楽見放題など)の利用料金
・通販で購入し、未決済のものなど
デジタル遺産の問題点
1.本人(故人)しかわからない状態になっている
デジタル遺産はパソコンやスマートフォン内にデータとして存在しているため、相続される方が気付きにくく、遺産から漏れる可能性が高いです。遺産が把握できなくても金銭的な価値があれば相続財産に含まれる場合があります。
デジタル遺産があると分かった場合でもスマートフォンやパソコンのセキュリティロックを解除しなければなりません。セキュリティロック解除時に一定回数間違えてしまうと初期化されることがあり、思い当たるパスワードを入力することはさけた方がいいでしょう。
2.遺産がどこにあるかみつけにくい
不動産や現預金などの遺産は部屋を探した時に見つかる可能性がありますがスマホやパソコンで管理しているデジタル遺産はデジタルの形で管理されているため、見つけるのが非常に難しくなります。
スマホなどのセキュリティロック解除ができたとしても、対象のアプリを見つけ、デジタル遺産を探す必要があります。ネット銀行の場合は通帳が発行されないため、亡くなった方以外の人が見つけるのが難しいことがあります。
3.定期サービスの支払いが継続している
オンラインスクール、音楽や動画などの定額課金サービスを利用していた場合、毎月定額料を払うことになるため、解約手続をしなければ支払いが続いてしまいます。遺族が契約情報を知らないことも多く見落としがちです。
4.相続税の追徴される可能性もある
デジタル遺産が後から見つかり、相続遺産に含めなかった事実に、故意があったと判断された場合には遺族に重加算税が課されることとなります。
デジタル遺産を管理する理由とは?
遺族(相続人)が見つけられなかったデジタル遺産は、忘れられたまま放置されてしまいます。そのため、生前からの対策が必須です。
ではデジタル遺産を管理するとどのようなメリットがあるのかみていきましょう。
【デジタル遺産を管理するメリット】
1.定額課金サービスを把握することで支払をすぐ止めることができ、不要な支払を回避できます。
2.遺産分割協議が終了後、デジタル遺産がみつかった場合はやり直ししなければなりませんがデジタル遺産を正確に整理しておくことでこれを防ぐことができ、相続手続きが滞りなく進めることができます。
※遺産分割協議とは相続人全員で誰が何を取得するかを話し合うことです。
3.デジタル遺産の存在に気付かず、後で見つかった場合に相続税の延滞税がかかったりする等、遺族に損害が発生する場合があります。デジタル遺産を相続しやすいように整理しておけば期限までに漏れなく申告でき追徴課税されることがなくなります。
4.電話帳やSNSなどの連絡先を整理しておけば、遺族が亡くなられた方の交友関係を確認でき、葬儀の出席者を把握することができます。
デジタル遺産の生前の管理方法
1.契約中の金融機関等を整理する。
対象の財産を見つけ出すのに非常に時間がかかります。相続や遺産分割手続きに影響していきますので、契約している金融情報のアプリなどスマートフォンなどの整理をしておきましょう。スマートフォンやパソコンのセキュリティロックの解除の方法を遺族に伝えておきましょう。
2.遺族に遺産の目録を見える形にする
遺産目録を作成し、デジタル遺産の内容を漏れなく記載しておくことです。その際、IDパスワード、登録用のメールアドレス、電話番号などまとめておきましょう。通帳等の重要書類と一緒に、厳重管理が必要です。
※遺言書にデジタル遺産の相続に関する内容を記載し、相続人が困らないよう誰に相続させるか具体的に明記します。
3.定期サービスを見直しましょう。
自動更新し、支払いがどんどん継続してしまいますので、不要なサービスは解約しましょう。
4.エンディングノートの作成
自分自身に万が一のことがあったときに備えて、自分の情報をまとめておくノートになります。エンディングノートや財産目録(財産の一覧表)を作成することで、財産の中身や処分の方法を家族に伝えることができますデジタル遺産の内容やアカウントのIDやパスワードを一緒に記載しておくと相続時の手続きが円滑になります。エンディングノートの内容は法的効果が生じません。
5.死後事務委託契約を結ぶ
亡くなられた後は次のような事務的な手続きや精算が発生します。
<例>
・行政への手続き(死亡届、健康保険等の申請)
・葬儀・火葬の手配
・病院などの退院手続き
・諸費用の支払(家賃、公共料金の支払いなど)
まとめ
デジタル遺産についての説明から生前に管理方法までご紹介していきました。ネットバンキング等デジタル遺産は増え続けているため、デジタル遺産の存在自体に気づきにくいという問題点やスマホ・パソコンから調べることになるため、とても時間や手間がかかります。
パソコンやスマホは他人に中身を見られることには抵抗もありますが、遺族が困ることのないよう生前のうちから対策を考えていくことが大切です。
最後までお読みいただきありがとうございました。