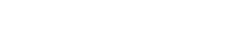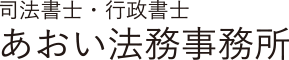相続相談
相続放棄
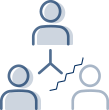
相続放棄とは
遺産相続はプラスの財産だけでなくマイナスの財産も相続してしまいます。マイナスの財産の方がプラスの財産より多い場合やマイナスの財産は相続したくないのであれば、相続放棄の手続きをする必要があります。
※相続人の間で、「この不動産は母が相続するから子供たちは放棄する」という意味合いの遺産分割とは異なります。(詳しくは遺 産分割で。)
相続放棄とは、故人の一切の財産を承継せず、放棄するという手続きです。相続放棄をすると「最初から相続人ではなかったもの」という扱いになります。そのため、プラスの財産は欲しいけれど、マイナスの財産は放棄するということはできません。 相続放棄した場合、借金などの負債を承継しないだけでなく故人の預貯金や不動産も一切承継しません。
相続放棄できる期間
相続放棄の手続きは
- 1.被相続が亡くなったことを知ってから3ヶ月以内に
- 2.家庭裁判所に対して、相続放棄の申立てをする
という手続きが必要です。
申立ては、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てします。

3ヶ月以内に相続放棄の手続きができなかった場合はどうするのか?
相続放棄の期限は、相続開始と自分が相続人となったことを知って3ヶ月以内【熟慮期間】です。原則として3ヶ月を過ぎると単純承認したこと(相続することを認めたこと)になり、相続放棄が認められなくなってしまうため、早期に相続放棄を検討しましょう。
しかし、現実問題として3ヶ月という短期間に相続財産調査を行い、相続放棄に関する書類を集めて、家庭裁判所に申立てを行うのはハードルが高いです。実際のところ3ヶ月を過ぎてしまうケースはたくさんあります。
3ヶ月経過後でも例外的に相続放棄が認められる場合
熟慮期間を経過してしまったことに特別の事情がある場合には、例外的に相続放棄が認められる場合があります。
-
〈判例〉
相続人が、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全くないを信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて、その相続人に対し、相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人においては上記のように信じたことについて相当な理由があると認められるときには、相続放棄の熟慮期間は相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識したとき、または通常これを認識しうるべきときから起算すべきものである。
(最高裁判所昭和59年4月27日)
-
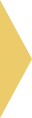
-
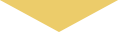
-
・マイナスの財産が全くないと信じていた
・被相続人と疎遠で、遺産や借金などまったく知らされておらず、知るのが困難な状況だった
このような場合は家庭裁判所へ申立てすることにより3ヶ月の期間を伸長することができます。
しかし、期限を過ぎてしまった後の申述は必ず受理されるわけではないので、相続調査に時間がかかりそうなら熟慮期間の伸長を申し立てましょう。
期限内でも相続放棄がみとめられない場合
熟慮期間中に遺産を処分してしまった【単純承認】の場合、相続放棄はできなくなります。
例えば
-
・被相続人名義の預貯金口座や証券、不動産などの名義を自分に変更した
-
・被相続人の遺産を売却し金銭を受領した
-
・遺産分割協議をした
-
・相続人が被相続人の債務を相続財産から払った(借金の返済など)
です
相続放棄に必要な書類
 共通の必要書類
共通の必要書類
・被相続人の住民票除票もしくは戸籍の附票
・申立人の戸籍謄本

-
 配偶者が申立てする場合
配偶者が申立てする場合
・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
-
 子が申立てする場合
子が申立てする場合
・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
-
 孫が申立てする場合
孫が申立てする場合
・孫の親の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
-
 父母が申立てする場合
父母が申立てする場合
・被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍(除籍、改製原戸 籍)謄本
・被相続人の子(父母から見て孫)が死亡している場合、その 子の出生から死亡までの全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
-
 兄弟姉妹が申立てする場合
兄弟姉妹が申立てする場合
・被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍(除籍、改製原戸 籍)謄本
・被相続人の子が死亡している場合、その子の出生から死亡ま での全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
・被相続人の直系尊属の死亡の記載のある死亡の記載のある戸 籍(除籍、改製原戸籍)謄本


相続放棄と遺産分割の違いについて
冒頭でもふれたように「遺産分割で何も相続しないので、借金も相続しない」とはなりません。遺産分割でプラスの財産を相続しないと決めたとしても、債権者に主張することはできません。マイナスの財産を一切相続しないためには相続放棄をすることです。
相続財産を相続しない2つの手続き
-
遺産分割協議と相続放棄
相談に来られる方の中に、「私は預金も不動産も相続しないから、相続放棄した。」とおっしゃる方がいます。相続財産は承継しないのですが、これは本当の意味での相続放棄とはなりません。
遺産分割協議とは、「どの財産を、誰が、どんな配分でもらうか、借金はどうするか」を相続人の間で約束することです。相続人以外の他人に主張することはできません。亡くなった人にお金を貸していた債権者は分割協議書のないように関係なく、相続人全員に対して返済を請求することができます。
遺産分割協議で「何も貰わない代わりに借金も一切負わない」というのと、裁判所で手続きする相続放棄とでは法的な意味合いが異なります。
相続放棄は裁判所に申し立て受理されることによってのみ成立します。相続放棄は亡くなった方の相続財産を一切相続しない手続きです。遺産分割協議と異なり相続人以外にも主張できます。はじめから相続人ではなかったという扱いになるため強力な効果があります。
-
-
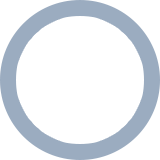
遺産分割
協議
相続人全員で協議をする。
相続人の間のみ効力がある。 -

裁判所に申し立てる。
一人でも可能。
何人にも効力がある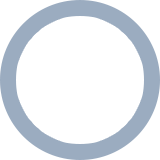
相続放棄
-
相続放棄手続きの流れ

-

書類の提出
被相続人が亡くなったのを知ってから3ヶ月以内に相続放棄に必要な戸籍謄本、相続放棄申述書、収入印紙、郵便切手を被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。
-

裁判所の
返信書類提出後、裁判所から「照会書」が郵送されてきますので必要事項を返答し返信してください。
-

相続放棄
手続き完了照会書が裁判所に届き、1週間から10日前後で「相続放棄申述受理通知書」が送られてきます。 そこで無事に相続放棄手続きが終了します。
-

書類の提出
被相続人が亡くなったのを知ってから3ヶ月以内に相続放棄に必要な戸籍謄本、相続放棄申述書、収入印紙、郵便切手を被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。
-

裁判所の返信
書類提出後、裁判所から「照会書」が郵送されてきますので必要事項を返答し返信してください。
-
相続放棄手続き完了
照会書が裁判所に届き、1週間から10日前後で「相続放棄申述受理通知書」が送られてきます。 そこで無事に相続放棄手続きが終了します。

相続放棄手続き費用
-
司法書士報酬
50,000円(税抜き)
※複数同時の場合は2人目以降30,000円(税抜き) -
必要書類取得(戸籍謄本・登記簿謄本)
1通につき1,000円
-
他(収入印紙、郵便切手)
実費
相続放棄手続き費用
-
司法書士報酬
50,000円(税抜き)
※複数同時の場合は2人目以降30,000円(税抜き) -
必要書類取得
(戸籍謄本・登記簿謄本)1通につき1,000円
-
他(収入印紙、郵便切手)
実費


Contact
お問合せ